えっ、それ方言なの?山口県の方言&活用形まとめ

中学生の時に「山口弁は標準語に近い」と、国語教師に教えられた。
理由は「幕末から明治維新にかけて、東京で山口県人が活躍したから」だと。
大学で東京に行き、そんなことはまったくのデタラメだという事がわかり、先生が全て正しいことを言っているわけではないことに気づいた18才の春。
そんな経験を経て大人になった私が、気になる山口弁についてまとめて見ました。
アナタはどれだけわかるでしょうか?
2019年9月3日 追記
読者の方から『これもあるよ!』とお声を頂きましたので追記しております。
この記事の目次
山口県の方言&活用形
破れた(やぶれた)
物が壊れることを「破れた(やぶれた)」という。
例:自転車が破れた~!

たお
峠のことを「たお」という。
例:牛ヶ峠(うしがたお)
場所により「だお」「とう」「どう」と呼ぶ場合もある。
もちろん普通に「とうげ」と呼ぶところもある。
びっしゃ
ずぶ濡れになることを「びっしゃ」という。
例:はぁ~びっしゃになったいねぇ~(もぉ~ずぶ濡れになっちゃたよ~)

ぬすくる
なすりつける、拭うことを「ぬすくる」という。
例:おめぇ~、濡れた手を俺のTシャツでぬすくんないやー
ひやい
冷たいことを「ひやい」という。
例:この井戸の水はひやい(この井戸の水は冷たい)
ひやくてびっくりしたときは「ひやっ!」という。
ちなみに大学時代に先輩から「意味はなんとなく分かるけどね」と笑われました。

「~ちゃ」・「~っちゃ」
語尾の~だよ。~なの!を「~ちゃ」「~っちゃ」という。
例:ほんとっちゃ(本当だって)
※東部はあまり使わない。そのかわり「~けー」「~じゃけぇ」を使う。
「~そ」・「~ほ」
また、西部地域は
何しているの? = なにしよるそ?
遊んでるの。 = あそんじょるほ。のように語尾に~そ、~ほ、を使う
また、掛け合わせることもある
例:「今からするほっちゃ!」(今からするんだよ)
じら
わがままやぐずることを「じら」という。
例:じらゆーたらいけんっちゃ。(わがまま言ったらだめだよ)
例:ほら、じらが出た。(ほら、ぐずりだした)
ちなみに「じら」を言う人のことは「じらくり」「じらくい」という。
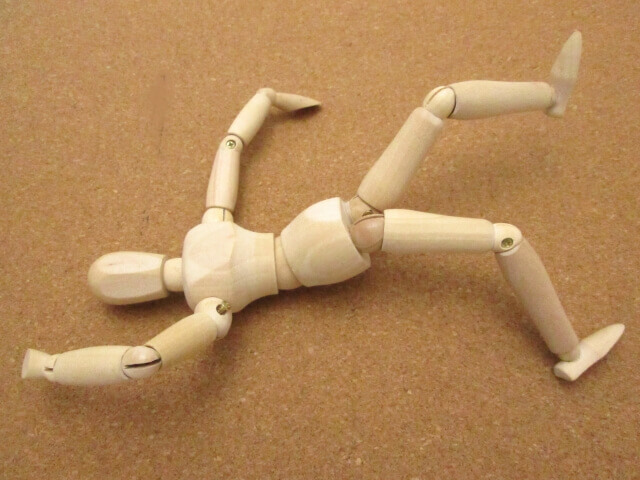
ギリ
つむじのことを「ギリ」という。
例:あんた「ギリ」が2つあらーね!(あなた、つむじが2つあるのね!)
やし
ズルをすることを「やし」という。
例:やしすんなっちゃ!(ズルすんなよな!)
たう
届くことを「たう」という。
例:体が硬くて手がたわん。(体が硬くて手が届かない)

なおす
片づけることを「なおす」という。
例:この食器なおしといて。(この食器片づけといて)
これも学生時代「はぁ?」って言われました。
かぶる
噛む、刺すことを「かぶる」という。
例:ぶとにかぶられたっちゃ~!(ブヨに刺されたよ~!)

よーけ
たくさんの事を「よーけ」という。
例:よーけあるちゃのぉ~(たくさんあるんだよねぇ~)
だいしょう
多少のことを「だいしょう」「だいしょー」という。
例:だいしょう集まったいね。(多少は集まったよ)
コショーのメーカーではない。
代償でもない。
めいぼ
ものもらいのことを「めいぼ」という。
例:めいぼが出来てぶち痛い。(ものもらいが出来てすごく痛い)
魚のそれではない

はぶてる
拗ねる、ふてくされることを「はぶてる」という。
例:はぶてるなーやぁー。(拗ねるなよー)
てっちゃんというあだ名の子がはぶてると「はぶてっちゃん」と一時的にあだ名が変わることがある。
にゃー
無い 共通語「無ければ」
山口弁「無けりゃー」「無けんにゃー」「無けらんにゃー」「無けらにゃー」
もはやネコ語である。

さで
動作を強調する魔法の言葉「さで」
これをつけるだけで、「投げる」「入れる」「捨てる」「込む」などの動詞が勢いづく。
「さで投げる」「さで入れる」「さで捨てる」「さで込む」
どねーもこねーも
「どうもこうも」を山口弁で言うとこうなる。
例:はぁ〜どね〜もこねぇ〜もねぇ〜っちゃぁ〜!
番外編
まりぃ~
驚きを表す言葉で「まりぃ~」という。
例:人から驚くことを聞いたときに「まりぃ~!」
これが山口県内のどこの方言かわかった方は凄いです!
かなりの山口つうです!
アナタはわかりますか?
追記
読者の方から「こんなのもあるよ」と教えて頂いたものを追記します!
つばえるも
ふざけるなの事を「つばえるも」という。
例:つばえるも!(ふざけるな!)
みてる
無くなることを「みてる」という。
例:万年筆のインクがみてる。(万年筆のインクが無くなる)
満ちるではない。その反対の意味である。
わや
無茶苦茶・ダメ・台無し、そういった様を表すことを「わや」という。
例:わやじゃ~(無茶苦茶じゃーん、台無しじゃーん)
これ、調べてみてビックリしましたが、北海道でも同様の意味で、使うようです。
また、関西圏や岡山などでも使うようですよ!
ちばけてる
ふざけている・子供じみている・みっともないなどを表す言葉に「ちばけている」がある。
例:ちばけんさんなやぁ~(ふざけすぎないでよー!)
これはかなり活用形があり、ぶりっこやチャラチャラして、なめたことをした時などを表す時もあるようです。
ちばけんなよぉ~・ちばけすぎよ!など
めんどぅない
みっともない事を「めんどぅない」という。
例:すみません。わかりませんw
読者さまからは「みっともない、から、みすぼらしさは引き算したカンジ?」と頂きました。
よさけない
足元が悪い事を「よさけない」という。
例:この道はよさけない(この道は足元が悪い)
ぶり・ばり・かち
魚の名前・・・ではなく、山口県を代表する方言「ぶち」同様、「とても」を表す意味。
例:ぶりすげぇー! ばりでけぇー!
たわん
届かないこと。
例:手がたわん(手が届かない)
すいばり
木や竹などのささくれ、トゲのこと。
例:すいばりが刺さったぁ〜ねぇ〜
かやれる
水が入ったコップなどが倒れること。
例:そねーな置き方したらかやれるっちゃ!
めげた
気力を失う「めげる」ではなく壊れること。
例:パソコンがめげたぁ〜やぁ〜!
ひらう
拾(ひろ)うのこと。
例:ゴミひらい
※調べると西日本で使われるようです。
よいよ
標準語で言う「まったく、もう!」などに近い。
呆れた時などに使う。
◯ーよ・◯ーね・◯ーや・◯ーちゃ
語尾の活用形。
例:はよしーよ・はよしーね・はよしーや・はよしーちゃ(全て早くしなさいの意味)
◯◯へまぁ〜・◯◯せまぁ〜・◯◯あるまぁ〜
否定するときに使う。
例:そんなことせまぁ〜(そんなことしないでしょー)
そんなことあるまぁ〜(そんなことないでしょー)
まとめ
山口県の方言&活用形まとめ、いかがでしたでしょうか?
山口県は西と東で方言の違いがあります。
また、県をまたいで使う方言もあったりします。
西部の「~ほ」は北九州の一部も使いますし、東部の「じゃけぇ」は広島でもお馴染みですよね。
WE Love 山口では、そんな山口弁をさらに調べて紹介していくつもりです。
次回もお楽しみに!
こちらもおススメです⇒山口に住んで驚いた方言(山口弁)9選




みてる
はご存知でしょうか?
標準語だと、満ちる、なニュアンスか感じられますが、逆です。
無くなる事を差します。
例:醤油がみてた。
北川さま
コメントありがとうございます。
確かに満ちるって方を想像しますね!
教えて頂きありがとうございます^^
ぶり
ばり
かち
があるんちゃ
コメントありがとうございます。
ありますね!
ぶり!
ばり!
かち!
日本の歴史で長く標準語は京言葉でした。そこから波紋が広がるように言葉の流行が広がりましたから、東夷のいた関東や山口県に似た流行の余波があっても不思議ではありません。それと明治初年の標準語を作った文部省の責任者は萩人でした。明治維新で活躍したのはほとんどは萩人です。その人の奥さんは京都の公家出身でした。女中は山手出身の元旗本の奥さんでした。下男は下町の男でした。標準語は大体、山の手言葉を中心としてできました。東京にも方言はありました。大正時代の青山小学校の学級日誌を読むと、先生が「オラやダンベ早めよう」と書いています。今もHの発音ができない人が多く、まっつぐと発音します。軍隊言葉には多少、萩弁の影響があるかもしれません。萩の丁寧語の挨拶は「わたくしはなになにであります」と言います。関東弁は無味乾燥ですから、日本語の美しさのためには今日の言葉が標準語になった方が良かったでしょう。
コメントありがとうございます。
山口出身者が活躍したというのは誇らしいですね。
関西弁はイントネーションが汚いのと坂東武者に戦に負けたから標準語になれなかったんだよ
理解しろ韓西部落カッペ京チョン土人
関西弁は声調言語からしてシナ朝鮮語と同じ語群
つまりはハプロYグループのOが圧倒的に多い関西人は正確には日本人ではないのである
日本人はハプロDを持つ民族を指す
東夷だのシナ人が使うであろう侮蔑語を使う時点でお察しだな
お里が知れる渡来チョン部落韓西土人
原爆で絶滅しとけ
ここの管理人はこの関西土人のコメントをなぜ消さない?壺県だから?
コメントありがとうございます。
この記事を投稿してこれまで、このような差別と考えられる投稿は過去一度もなかったのですが、とても残念です。
「ハプロYグループのO」「関西人は正確には日本人ではない」 などとコメントありますが、日本人は海洋民族であり混血民族であることはご存知でしょうか?
起源の考え方次第かと思います。
私自身、国や人種の違いなどで何か優劣が決まるものではないと考えており、すべての人種が仲良く生きていけたらとそれでいいのでは?と願っております。
どちらにせよ、あ様のような発言は日本人をも下げるような発言かと推測します。
本来であればこのコメントはこちらで削除することも可能ですが、残しておこうと思います。
デジタルタトゥーはご存知でしょうか?ちなみにIPアドレスで検索もできます。
あ様にとっても都合がよろしくないかと考えます。
削除される際はご自分で削除されてください。
山県有朋は人を選ぶ時は人を出身地で選ばない。才能で選ぶと言って居ます。人は才能と人を見る目です。萩人が活躍できたのは毛利敬親の目が大きいでしょう。才能がなく、人を見る目もないと悲劇喜劇が起きるのは諸兄ご存知の通りです。
面白い記事でした。
私は県西部の中学校から東部の学校へ進学したので、「〜ほ」を笑われたり、「すじひき貸して」が通じなかったりしたものです。
山口県は位置的にいろいろな方言の影響を受けていますね。
下関のオジ様方は、「よぃよ仲の良ェ友達」のコトを「ちんぐー」と言います。韓国語の「チング(=友達)」からきていると思われます。
古くから、交通の要所だったのでしょう。
Shinさま
すじひき!!! 確かに使っていました!
ちんぐー!私も初めて聞いたときは???と思いました。
チングーは、朝鮮語で友達です。
下関は、朝鮮人が多く住んでいますから。
コメントありがとうございます!
『ようさけない』は汚い、汚れているの意味で、明治生まれの祖母(萩生まれ、萩育ち)が使ってました。
ぞうりで遊んで帰ると『よーさけない足で座敷に上がっちゃいけんよ。足をあろーてから上がりんさい』と、言われてましたね。
コメントありがとうございます!
「ようさけない」は情けないなどのニュアンスでも使われますね。
世が世なら、山口弁が標準語になってたかも…
コメントありがとうございます!
そうだったとした面白いですねw
「せんない」って山口の中でも、さらに限られた地域でしか通用しない言葉です。どこでしょう?言葉の意味はなんだと思いますか?
コメントありがとうございます!
地域は特定できませんでしたが、言葉の意味は使うシーンや人により意味合いが変わってくるようです。
「めんどくさい」「つまらない」が一般的意味のようで、「仕方がない」「せつない」「つらい」などの意味合いでも使われるようです。
山口県中部在住ですが
『せんない』めちゃめちゃ使いますよ!
コメントありがとうございます!
中部では使われているのですね!!
「はなえて」って方言ですよね? 意味合いは、わざと、故意にとかです。
他には、お皿を「てしょう」って言ったり。。
コメントありがとうございます!
「はなえて」「てしょう」はじめて知りました!
山口弁深いですね(^^)
山口県人は「拾う」を「ひらう」と言いますね。
コメントありがとうございます!
確かに「ひらう」って言いますね!
めんどーない
めんどーない格好せんことや!
作る のことを
こさえる、こしらえる
うちの親は
独身男性のことを「ちょんがー」って言います。
韓国語の총각「チョンガッ」から来てるんだと思います!
ふざけることを そばえる とも使います^_^
姉弟でちょっかいだしてたら、「そばえなさんな!」ってよく怒られました(笑)
これは山口弁なのかわからないですけど、
おばあちゃんおじいちゃん、お母さんに
おバカって意味で「ぱーぷりん」って言われてました。
お灸のことを「やいとう」っていいます。
コメントありがとうございます!
まだまだ沢山ありそうですね!
ぶち=すごい というのもあります。
コメントありがとうございます!
ぶちに関しましてはこちらにまとめさせていただきました。
よろしければこちらもご覧くださいませ^^
https://we-love.yamaguchi.jp/yamaguchi-aruaru/yamaguchiben
よいよ
えらい
なかろう(ないよね)
なんか使いますね
後、小野田あたりでは
お使いしました
って近所の人が言います
ご足労しましたねって意味なのかな?
なんかもっとありそうですね
気がついてないだけで
コメントありがとうございます。
確かにもっとたくさん山口弁ありそうですね^^
カメムシの事をホウムシって言いませんか?
出て来たのを見て思い出しました(^_^;)
東部出身、中部在住です。
コメントありがとうございます!
ホウムシ言うエリアありますね^^
調べたところホウジと呼ぶところもあるようですw
物の呼び名を調べるのも面白そうですね!
方言かどうかが分からないけど、
大声で呼ぶ様なことを「たっける」と言ったり
神経痛のような痛みを「はしる」と言ったり
行きなさいが「行きーよ」とか「行きーね」になったり
方言なのかな?
返信遅れて申し訳ありません!
コメントありがとうございます。
たっける 〇〇ーよ 〇〇ーね は方言だと思われます^^
明治生まれか大正の萩地方女言葉だと思うけれど、明治 萩生まれのの祖母世代が使っていた「おことうござりました」
誰か 分かる人はいませんか?おぼろな記憶で「お疲れさまでした・お忙しかったですね」というニュアンスだったように思うのですが。
コメントありがとうございます!
「おことうござりました」は初めて聞きました!
ネットで調べてみましたが該当するような内容は出てきませんでした。
「おことゆうございます」というのは「お忙しゅうございます」という意味で使われる挨拶言葉です。「事が多い」というのが語源でしょうね。なお、これは今でも祇園の舞妓さんたちの間で使われていますよ。
コメントありがとうございます!
>これは今でも祇園の舞妓さんたちの間で使われていますよ。
そうなのですね!!
まりぃ~のところ、
どこの方言<か>分かった方
では?
コメントありがとうございます。
お気づきいただきありがとうございます。
修正させていただきました!
「へま~、せま~、あるま~」
ま~に否定の意味がありますよね?(笑)
「〇〇言うちょらへま~?」〇〇(なんて)言ってないでしょ?
「せま~や」しないようにしようよ。
「あるま~?」ないでしょ?
近所のおばあちゃんが「まあ、のんた、そねぇなこたぁあらへま~がな?」あらあなた、そんなことはないでしょ?って言ってたなぁ(笑)
コメントありがとうございます!
〜〜ま〜、
確かに言ってますねー。
「そんなこたぁ〜あるまぁ〜」とかですよね^^
ただ最近は聞くことも少なくなりましたねー
他の方からも語尾に関する内容いただいています。
語尾も記事内に追加した方が良さそうですね^^
方言短歌をご存知ですか。中川健次郎、「山口県の方言」『講座方言学8 中国・四国地方の方言』、1982、国書刊行会、ISBN 4336019797 これは中川健次のことなのでは?
今は亡き私たちの短歌の師でした。その方の作られた方言短歌です。
すまんのうへんじょうこんごう言うちょってはあ日が暮れたまた来いされよ
のけぞってじらくる孫を抱きあげる嫁の笑顔をごろうじませい
てんくらのねんごう言いのきもやきが異なげな歌を作っちょるいね
家屋敷みてるまで飲みし曽祖父のえいころはちべい我につながる
のうくれでおうどうもんのじらくりでへんくうたれとはおどれのことよ
ちゅうにごっぽうどひょうしもないかばちたれへてからえろうよばれましたのう
ちゅうにまあほうとくないがあねさんのお好きなようにしんさいせいな
などなど、言葉遊びの短歌ですが面白いですね。
コメントありがとうございます!
私ほぼ読めませんでしたっ!!
山口県東部に生まれて50年の生粋の山口県民ですが、ここに書かれている方言の3分の1くらいしか理解できませんでした。
広島の方言なら99%くらいは理解できるのですが。
コメントありがとうございます!
私自身、東部・西部両方に住んでわかったのですが、結構東と西で方言が違いますね。
東部の方は 「ほ」 は使わないですものね^^
「するほっちゃ」とかも 笑
楽しく拝見させて頂きました
私は山口が大好きで山口弁も大好きです
祖母に育てられたお陰?か方言には馴染みがありすぎてもはや死語となっている方言を使ってしまうこともあります
それは方言なのかどうなのかもわかりません
お年寄りには通じるのでお年寄り言葉とも言えるかも知れません
その中に「ける」「いびる」というのがあります
もちろん蹴るでもいじめることでもありません
なんと同じ様な意味なんですよ
例:この具材をけっちょって、この具材をいびっちょって
…と使います
両方とも「この具材を炒めておいて」と言っています
コメントありがとうございます。返信遅くなり申し訳ありませんっ!!
「ける」・「いびる」をその意味で使うとは知りませんでした!
山口弁奥が深すぎますね!!
19年7月に投稿して 解決しなかった「おことう・・・」解決しました。2歳年上85歳の友人が覚えていました。意味は「お忙しいところ・・・」その後に「ようおいでましたね!」などの言葉を続けて使っていたそうです。つまり、「おことうござりますのに、ようおいでましたのんた!」かな! 記憶違いでなかって嬉しい(^_-)-☆
コメントありがとうございます。返信が遅くなって申し訳ありません。
解決してよかったです!
『てれんこぱれんこ』
標準語だとなにになるんだろ?
タラタラ フラフラ とかになるのかな?
『おはようございました』
東部エリアでしょうか、なぜか過去形になる語尾
『わて』
谷間とか斜面と平地の境
『おいでませ』『おいでました』
ニュアンスで状況が違う
『よぉ』
よく・ようこそ
例よぉ おいでました
コメントありがとうございます!
そういえば宇部出身の方が「てれんこぱりんこ」(その方は《 り 》)と言われたのを思い出しました^^
「おはようございました」もおじいちゃんおばあちゃんが使っているのを耳にしますね。
「てれんこぱれんこ」は標準語では「ちんたらちんたら」ですね。
楽しく拝見させていただきました。
あと
疲れたを「えらい」といいます。
例 あーえらかった。
意味 あー疲れた。です。
コメントありがとうございます!
「えらい」こちらは定番の山口弁ですね^^
ちなみに「えらい」に関してはこちらの記事に掲載しております。こちらも読んでいただけると嬉しいです。
https://we-love.yamaguchi.jp/dialect/yamaguchiben2
私は下松市出身なのですが、下着のパンツの事を「パンズ」と言っていました。
母「新しいパンズ買うちょったよ!」
コメントありがとうございます!
おばあちゃんがそう言っていたのを思い出しました^^
実際の山口弁を使うのは山口市を中心にした
真ん中あたりの人。
周南、防府、山口、宇部周辺がホントの山口弁使う人。
周南より東、岩国、柳井辺りは広島の影響が強いので広島弁
下関も北九州に行く人多いのでこれも北九州の言葉がまじってるし、
更に旧田万川、須佐町辺りは益田が近いので島根の言葉が使う人多い…〜ろ、みたいな。
コメントありがとうございます。
なるほど、地域によって他の県の方言も入ってしまうのですね。
〇〇やろ
とか
たとむ(たたむ)
もある!
コメントありがとうございます!
たとむっていうんですね